06建築おもしろ話
家を持ち上げる揚家工事2025年06月14日
足助の古民家リノベーションは、解体が終わり揚家工事が無事に終わりました。
これから、基礎工事に入っていきます。
さてここで、今回は揚家工事について書こうと思います。
揚家(あげや)とは、どんな工事かと言うと、読んで字のごとく「家を上げる」工事です。
えっ!!家って持ち上げることができるの??と思う方も多いと思いますが、曳家・揚家専門業者さんがいるくらい建築工事としては認識されています。
とはいっても、昭和の後半からは解体して建替えること普通になってしまったので、ほとんど揚家工事を観ることはなくなりました。
今回の物件は、重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物に指定されているので、保存・修理をするために揚家をしました。
揚家工事をした写真がこちらです。


赤矢印のところが柱の足元です。家が持ち上がっていることが分かるでしょう。
今回の揚家は、柱と柱を鉄骨で両側から挟み込んで、その鉄骨を箱ジャッキで少しずつ持ち上げて、
枕木を1段ずつ鉄骨の下に積み上げて家全体を浮かすのです。
その時に使うジャッキが、先述の「箱ジャッキ」と呼ばれるものです。
油圧ジャッキと同じですが、これは建築工事用に作られたものです。

この箱ジャッキを使って持ち上げたんです。
建物全体を一度に揚げることはできないので、部分的に少しずつ揚げて、最終的に家全体が持ち上がるという訳です。
少しずつ持ち上げていく工事なので、揚家工事が無事に完了できたのは1週間後でした。
建物自体の損傷がかなり激しかったので、揚家工事している時に崩れないか不安でしたが、さすがは揚家専門業者さんですね。
無事に家を持ち上げる事ができました。
この後は、基礎工事と柱の足元の損傷があるところは新しい柱に継ぎます。
これらもまた、職人技です。楽しみですね。
天王社さんの着工前確認がありました。2024年05月18日
先日、豊田市足助地区の重要伝統的建造物群保存地区にある天王社さんの
修繕工事に当たって、文化財課さんとの着工前確認がありました。

解体前に今回の工事で、取替える部材と既存のまま再用する部材の確認をします。
取替える部材が多すぎると建替えてしまったように見えてしまいますし、
既存のまま再用する部材が多すぎると修繕工事の意味がなくなってしまいます。
その文化財として保存しつつ、今後も地域のお社として残していく為に、
とても大切な打合せなのです。
この打合せが終わると、いよいよ着工です。
現在の姿から大きく形が変わる訳ではありませんが、
修繕工事で年末には綺麗になるのが楽しみです。
 着工前正面より
着工前正面より
 着工前・北西角より
着工前・北西角より

 明治四年に上棟
明治四年に上棟
設計のワークショップを開催しました。2023年10月02日
先週末の土曜日に、
“とよたならではを体験”することができるプログラムを集めた事業であるとよたまちさとミライ塾+の一環で、
設計のワークショップを開催しました。

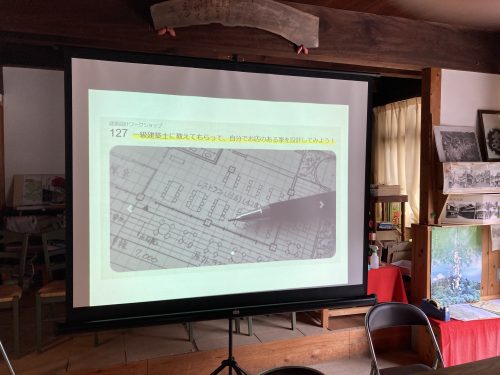
豊田市には、足助町に重要伝統的建造物群保存地区(以下「重伝建地区」)があります。
その街並みを散策しながら、重伝建地区の一角にある敷地を使って、
店舗のある住宅を設計するワークショップをしました。
最初に、住まいを設計するために考えることを簡単に解説してから、
街並みの景観を意識して設計してもらいました。
参加者さんは、自分なりに一生懸命考えていました。
豊田市に重伝建地区があって、その景観で街の歴史を感じてもらえると嬉しいです。
また、設計というものに触れてみれ、
設計の仕事について興味を持ってもらえるともっと嬉しいです。
このワークショップは、12月2日(土)にも開催します。
一級建築士に教えてもらって、自分でお店のある家を設計してみよう! | とよたまちさとミライ塾 (toyota-miraijuku.com)
是非ご参加ください。
とよたまちさとミライ塾でプログラムを開催しました。2018年10月23日
先週末から始まった『とよたまちさとミライ塾2018』で
風とガレも豊田の魅力を発信するため、
「テーマは『屋根』。日本建築の屋根を徹底解明!」の
プログラムを開催しました。
昨年に初参加して、今年は2回目の参加です。
豊田市足助町には
国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている
街並みがあります。
その街並みを散策しながら、
日本建築の魅力を知ってもらう企画をしました。
昨年は、意外と気が付かない日本建築の
おもしろい所を探しながら散策する内容でした。
今年は、もう少し踏み込んで日本建築の『屋根』について
分かりやすく解説しました。
観光地でよく観る檜皮葺き(例:二条城唐門の屋根)や
杮葺き(例:桂離宮中書院)の中がどういう仕組みに
なっているか、瓦の種類や屋根のかたち、名称、など
写真を見てもらいながら解説しました。

解説した後は、実際に足助の街並みを見ながら、
日本建築の魅力を楽しんでもらいました。
参加者さんからの声
『気づきにくい点を説明してもらえて、
楽しく歩けました。』
『私は建築のことは全然わからないのですが、
わからないからこそ「なるほど」と
興味をもってお話を聞くことができました。
あと、吉谷さんが楽しそうに話されているのが
とても印象的で、本当に日本建築が好きなんだなぁと
お話に引き込まれていました。』 等
参加者さんから楽しかったと言ってもらえて良かったです。
また、機会がありましたら企画したいと思います。